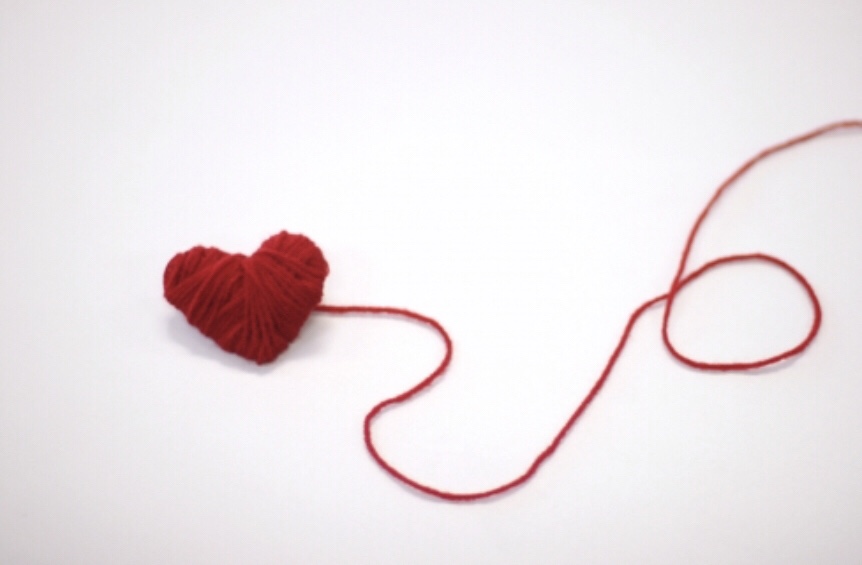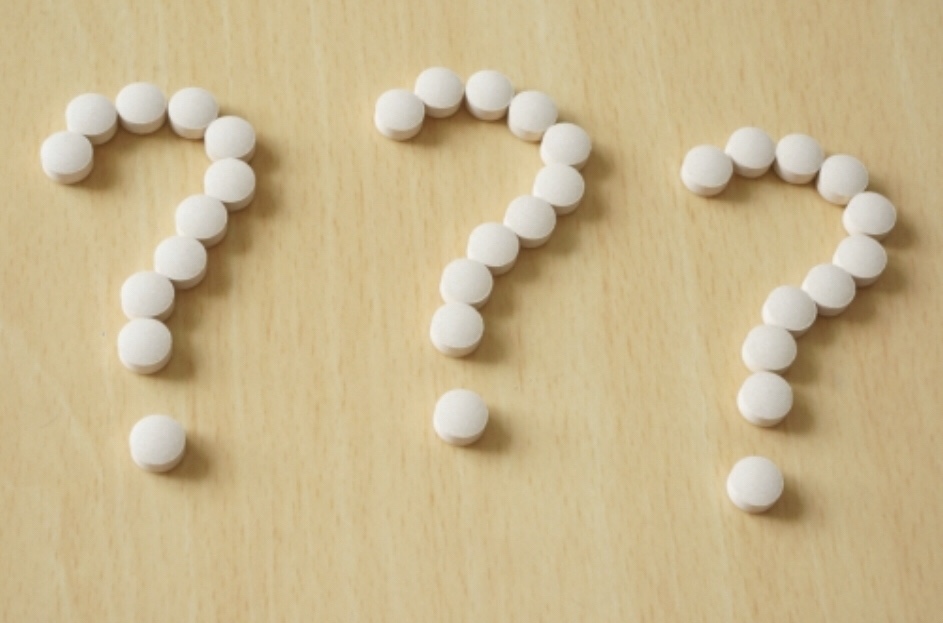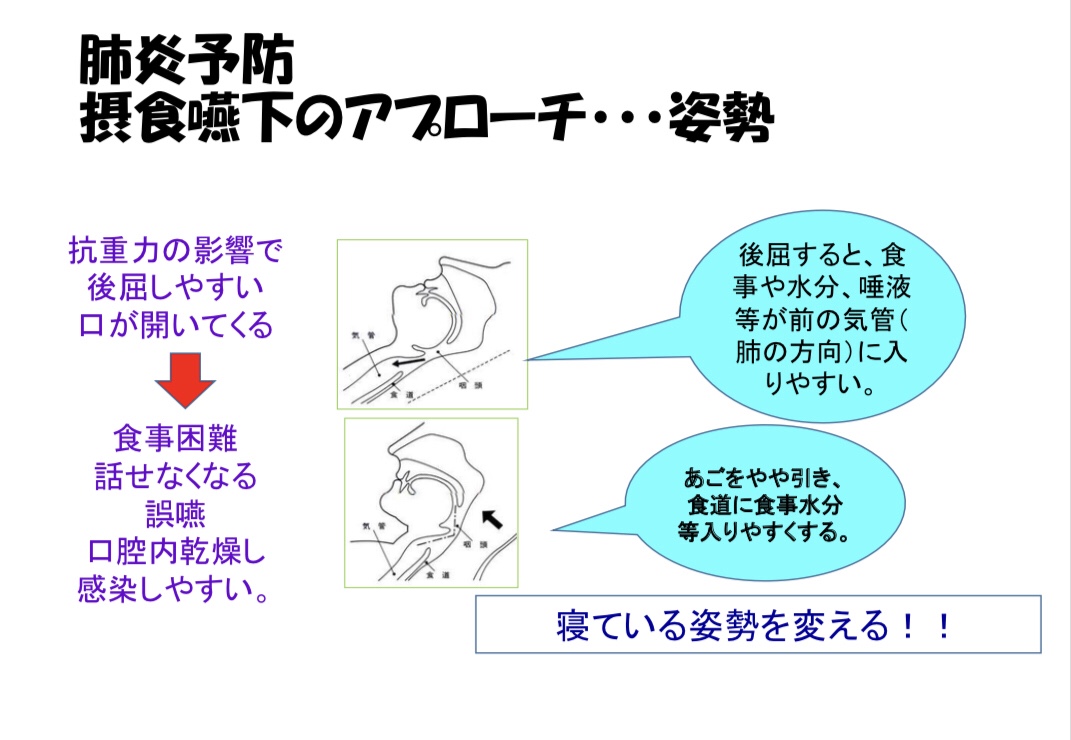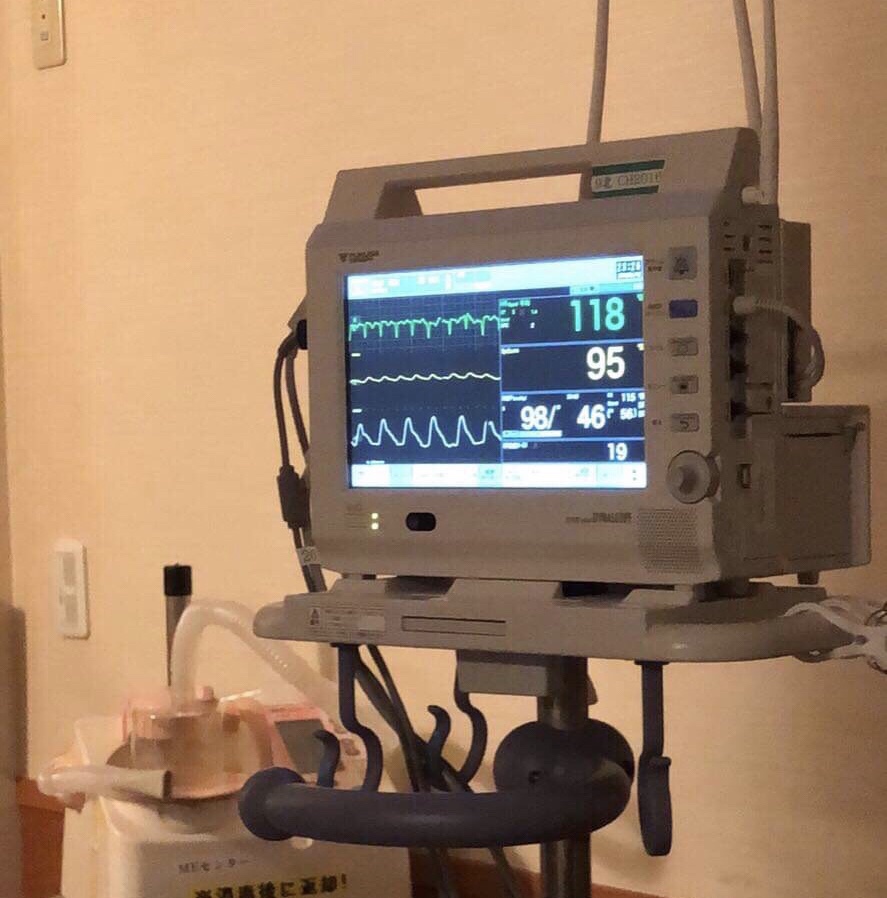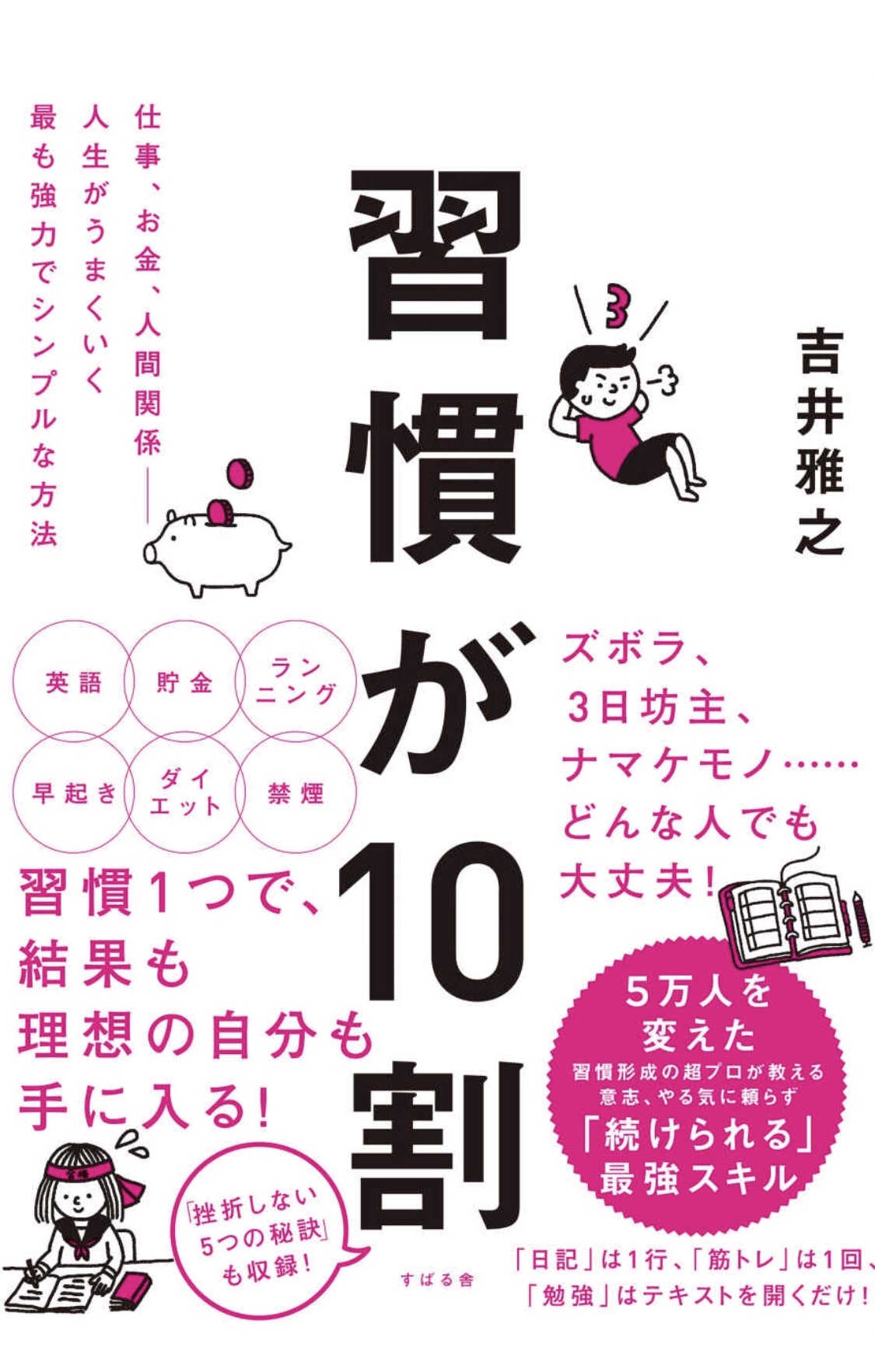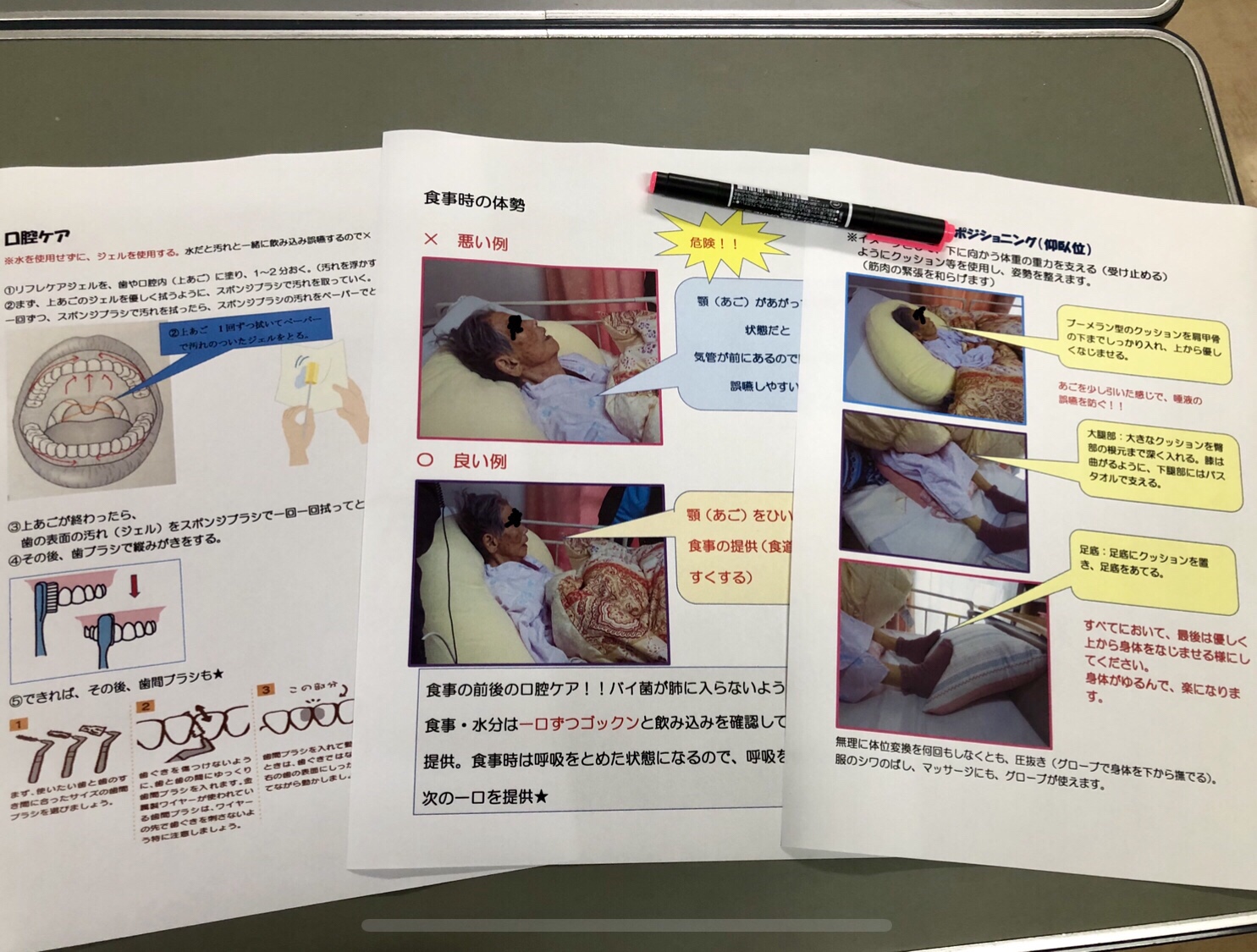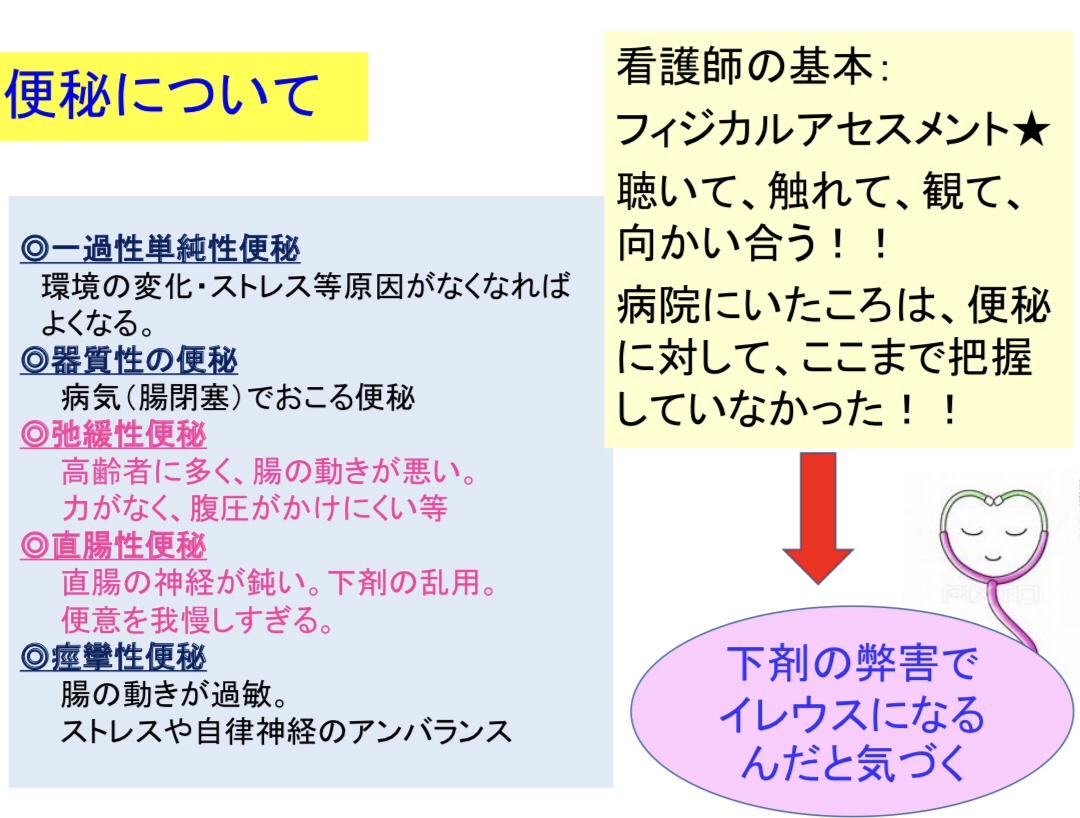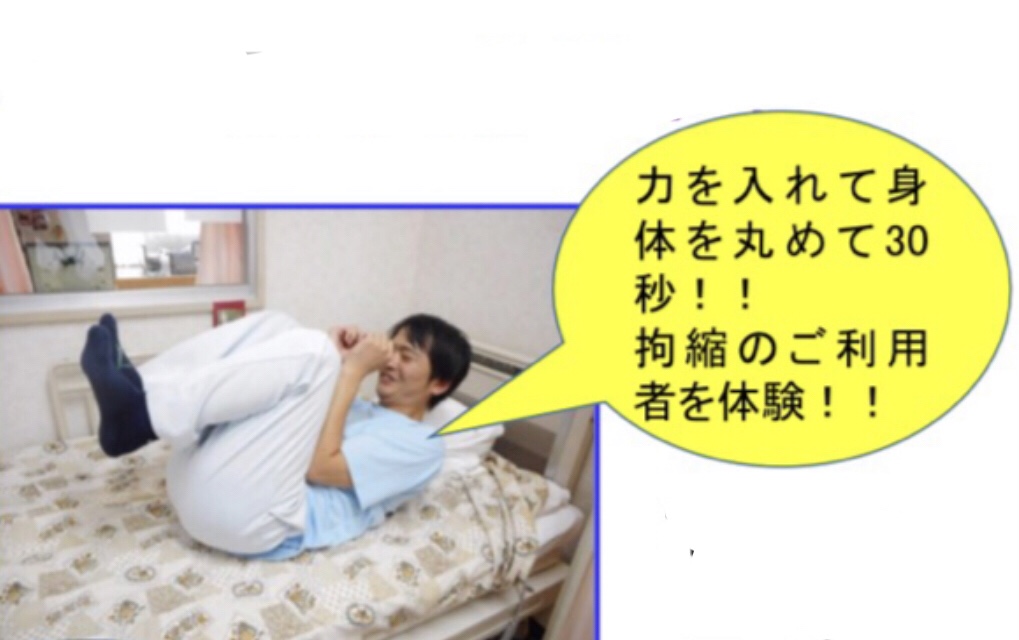お看取りや認知症のご利用者が増えている介護現場。
スタッフも頭の中がそれぞれ、大変で埋め尽くされてしまうと考えが定まらず、疲弊してしまう。

そういう時こそ、しっかり見つめることが大切。
ご利用者の動き、私たちスタッフの動きの見える化。環境の見直し。
入所して環境が変わって不安で、立ったり歩いたりされる認知症のご利用者。
ここはどこだろう?あなたは誰?すごく不安な様子がわかる。
過去を知る、そして、
いつもよりしっかり24時間観察、記録をし分析する。(期間を決め集中)
どういう時に不安な行動をされるのか?
どんな表情や行動をされるのか?
逆に、どんな時に表情がよくなるのか?落ち着かれるのか?笑顔は?
会話の一つ一つを聞き取る。
その意味をひもを解く。排泄は?食事は?体調は?
しっかり多職種チームで助け合う。強みと弱みの視点も大切。

●人的環境を整える。
人との馴染みを💕スタッフだけでなく他の利用者との相性を探りながら、席を隣にしてみたり。
ご家族の協力、ここに馴染むために顔を見るのはじっと我慢。様子を伝える。
●馴染みの場所は物をどうする?
ここに座ると人の動きが見えすぎて、更に不安になるのでは?
椅子は普通のが良いのか?
ソファで寄り添うようにくつろいでいただくのは?外が見える方が良い?安心できるものは?
ぬいぐるみ?毛布?馴染みのものは?など。

夜間不眠時、
スタッフもトントンと横に付き添い過ごす。時間がないのではなく覚悟を決め、集中して横につきそう。
他のご利用者との影響は?
何時間睡眠がとれた?
1日の生活リズムは?
根気よく、スタッフはよく頑張ってくれてます😊
利用者が不安であるとともにスタッフも感情が引き込まれないように、責任者は声かけ、毎日の短時間のミーティングのすり合わせ。
毎回、新しいご利用者もスタッフが根気よく声かけあい付き添うので、いずれ落ち着いてきます。
行動を否定をせず、受け入れてうちのスタッフは優しいなといつも思います。本当に感謝😊
とりあえず言いたいのは、
混乱したり大変な時は、
集中して見つめて、分析して明確にしていくこと。(見える化)
スタッフ同じ動きにしていき、混乱をなくしていく。
安心したら、きっと笑顔になるから😊
でも、これって、認知症の方だけに当てはまらないよね★

















 ※ 葬祭業の新保くんは、グリーフケアについて学んだと語る。訪問看護師(坂下さん、窪田さん)は聞き入る。
※ 葬祭業の新保くんは、グリーフケアについて学んだと語る。訪問看護師(坂下さん、窪田さん)は聞き入る。 ※ 葬儀のことだけでなく、不動産業も営んでいた菅野くんは、空き家問題のことも気になると。
※ 葬儀のことだけでなく、不動産業も営んでいた菅野くんは、空き家問題のことも気になると。 ※ 司法書士の立場から、浜田くんは、亡くなる前に備えてこくとよいことを語る。備え方を間違えると無駄になってしまうので正しい知識は必要だね。大体、司法書士って何?から(笑)
※ 司法書士の立場から、浜田くんは、亡くなる前に備えてこくとよいことを語る。備え方を間違えると無駄になってしまうので正しい知識は必要だね。大体、司法書士って何?から(笑)